竈門炭治郎の実家はどこにある? 鬼滅の刃の出身地は雲取山
東京都の西方で、空の青さを反映して輝く湖、奥多摩湖。

新宿の高層ビル街からはじまる青梅街道をひたすら西へ向かえば、車はいつしか山に入り、奥多摩湖畔を走る。
ここも東京だが、このあたりまでくると丘陵にしがみつくような家屋や、猫の額ほどの段々畑の景色が、まるでネパールの田舎に来たみたいな感じ。

炭治郎の出身地は奥多摩
竈門炭治郎の出身地とされる雲取山は、奥多摩湖から北へ6kmほどの稜線にある。竈門家の場所はそのふもとのどこか。たぶん炭治郎くんも家族もこのあたりを歩いたことがあるだろう。
ただし奥多摩湖は昭和37年に小河内ダムの完成によってできた人造湖だから、若き日の炭治郎くんは見たことはないはず。もしかしたら晩年にここを訪れたことがあるかもしれないね。
炭治郎の家は雲取山のどこにあったのか?
鬼滅の刃の物語から判明している、竈門家の自宅に関する情報。
- 公式Bookによれば、出身は東京府雲取山
- 自宅は山中にあるが日帰りで町へ徒歩で炭の販売にでかけられる
- 道は途中まで車が楽に通れそうな幅で、炭治郎を泊めてくれる人家もある
下の写真が、奥多摩の眺望だ。鬼滅の刃第1話の舞台となったのはこのエリア。下方に見えるのが奥多摩湖。写真中央から右側にかけての主稜線上に、すこし飛び出ている頂が東京都最高峰の雲取山(くもとりやま)2017mだ。
 南側から見た雲取山。下方に奥多摩湖
南側から見た雲取山。下方に奥多摩湖雲取山は東京都・山梨県・埼玉県の1都2県の境でもある。
また、雲取山2017m・妙法が岳1332m・白岩山1921mの3つの頂を合わせて三峰山(みつみねさん)といい、名付けたのは第12代天皇の景行天皇と伝えられている。三峰山の北側に三峯神社という有名な神社があって、埼玉県の秩父駅からは路線バスでも行けるたいへん人気のお参り場所だ。
自宅に近いことから炭治郎くんもお参りに何度もいったことだろう。ただし東京都側からは現在でも山道を歩いてのみたどり着ける。
 毎日大勢の参詣者が訪れる三峯神社
毎日大勢の参詣者が訪れる三峯神社炭焼きを生業とする竈門家の家が、雲取山の頂上付近にあると思っている人が多いようだが、炭焼職人の自宅は人里からそう遠くもなく近くもないところにあるもの。
そして炭焼き小屋は、炭の原料となるナラノキやブナが標高1500m以下に多く分布することからふつうはそれ以上標高が高いところにはない。
 三峯神社から見た雲取山。炭焼平は写真の左外にある
三峯神社から見た雲取山。炭焼平は写真の左外にある三峰山の一角、妙法が岳に炭焼平(すみやきだいら)という炭焼き釜の跡地がある。
竈門家が炭焼き釜をどこにいくつ持っていたかは不明(ふつう、炭焼職人は複数の炭焼き窯を利用している)だが、ここ炭焼平の釜を利用していた可能性はある。しかし自宅もこのあたりにあるとしたら炭治郎くんは埼玉県民となってしまう。したがってここに自宅があるということはありえない。これらのことから推定される範囲は絞られてくる。
- 雲取山の北側は埼玉県
- 雲取山の東側は山梨県
- 雲取山の南側は尾根が続いていて人は住めない
地形からみて雲取山の東麓の日原しかない。竈門家の住所は東京府西多摩郡氷川村大字日原(現在の東京都西多摩郡奥多摩町日原)だ。日原の読みは「にっぱら」。

竈門家は、日原川の渓谷に近い山腹のどこかにあった。上の立体地図でいえば「雲取山」と「日原」の中間あたりであろう。下の地図なら都道204号線を「日原鍾乳洞」を通り過ぎて西へ行ったところのどこかにあったはず。

現代では、炭治郎くんが自宅へと歩いた道は都道として整備されているのだ。日原鍾乳洞へはJR奥多摩駅から路線バスがある。炭治郎くんも現代ならバスを利用したろうか。いや業者だし家に自家用車があるか。しかし本人は18歳未満で免許はとれないから車の運転はできないなあ。
日原鍾乳洞は人気の観光地になっていて連休中はマイカーで渋滞することもある。こんな道だ。
日原の鍾乳洞は、江戸時代は修験道の山伏が修行していた洞窟。明治以降は観光客がやってくるようになり、行者の子孫がたいまつで案内していたそうだ。竈門家の先祖もここで修行をしたことがあっただろうか。現在ではライトアップされて歩くのは簡単。

竈門家の水源は日原川
映画「無限列車編」で、炭治郎くんが夢の中で水を汲みに行く川は日原川に違いない。川幅がやや広く、流れが穏やかな様子からして現在の「渓流釣場」のあたりのような雰囲気だが、そこは両岸が急峻で人が住める環境ではないし画面にみられる竈門家近辺の地形とも異なる。竈門家に通じる道の両側には狭い畑と田をつくれる程度の平たい土地があるはずだ(186話でうたと縁壱が出会った場所)。もう少し上流のどこかだろう。
Sponsored Links
多摩川の源流、小菅村に到着
さて、奥多摩湖を過ぎて車を走らせるともう人家はほとんどない。東京都から埼玉県へ、このあたりでは自動車が通れる道はないが、青梅街道は狭く曲がりくねって山梨県へ通じている。かつては徒歩のトレッキングルートという感じだったことだろう青梅街道を走っていると、まもなく「山梨県」「小菅村」と書かれた簡素な標識が出迎えてくれた。

国境からさらに青梅街道を10分ほど走って、山梨県小菅村の集落に到着。

大正時代と変わらない風情である(そんなことないか)。炭治郎が家から炭を売りにいった町がどこなのか、物語に町名が出てこないから分からなくて、たぶん奥多摩町なんだろうけど、もしかしたらこっちの小菅村かも、と思わなくもない。小菅村は多摩川の支流の源流があって、街道沿いに温泉宿がいくつか並んでいる。一泊旅行にきてもよかったかも。
まずは村内を散策してみる。



村外れには、いっときは国宝に指定されていたこともある鎌倉時代の古刹、長作観音堂があるそうだ。そっちは遠いからあとで行ってみよう。おなかが空いたのでランチを食べに、道の駅へ。

道の駅 こすげ の石窯で焼くピッツァがわりと有名らしくて、今日はこれを食べに来たのだった。注文したのは小菅産ヤマメのアンチョビときのこのクリームピザ。

小菅村はヤマメが名物だそうだ。それなら、ヤマメをトッピングしたピッツァを味わおう、と思って注文したのだが、出されたピッツァにヤマメは載っていないみたい…? 生地はパリっとしていて、チーズはふんわりとして、いい触感だった。
食べながらよくよく見たら3mm四方の小さなカーキ色の小片がチーズの上にいくつか載っている。どうやらこれが「ヤマメのアンチョビ」らしいと気がついた。ヤマメの味はしないくらい小さいけど、ピッツァはおいしくいただきました。
ピッツァを食べたら、眠くなってきた。炭水化物はどうしても眠くなる。標高が高くて寒いし、今日はもう家路に就くとするか。長作観音堂はまた次回お参りに来ることにしよう。
再び東京へ
というわけで来た道、青梅街道を戻ることにした。東京都に入るときに「東京都」の標識が午後の陽を反射して、輝いて見えた。
 You are entering Tokyo Metropolitan.
You are entering Tokyo Metropolitan.鬼舞辻無惨が竈門家を襲った際、彼はどういうルートでここまで来たのだろうか。大正初期には、青梅線が日向和田(ひなたわだ)まで敷かれていて、新宿駅から立川駅経由で一日に6便の列車があった。
鬼舞辻無惨は終点の日向和田駅で汽車を降りてから、日原までの24kmを歩いて来たのだろうか。
それとも反対側の甲斐からはるばる歩いてきたのだろうか。もしそうなら、この峠を越えたことだろう。当時のこの峠はトレッキングルートみたいな感じで、ここから「東京府」という標識もなかったんじゃないかな。
もっとも、13話のころの鬼舞辻無惨には人間の妻子がいて、不自然に家を空けることは妻の不審を買うからできない(たぶん)し、なにより昼間は外出できないから列車に乗ることもできない。空間を飛び越えてとつぜん雲取山に現れてことを済ませたのだろう。青梅線を日向和田駅で降りてから24kmを歩いて竈門家に来たのは冨岡義勇だろう。
鬼舞辻無惨がこの峠を歩いた可能性は低そうだ。しかし竈門炭治郎くんは炭を売るためかなにかでこの道を歩いたことがあると思う。
鬼滅の刃、竈門炭治郎くんの実家に関する考察でした。










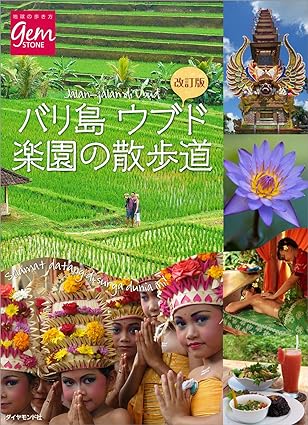


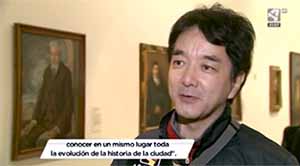

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません